マスカルチャー
マスカルチャーとは通常、マスメディアの集中生産プロセスから生まれた文化のことを指します。 しかし、この用語の地位は、Swingewood (1977) がこの用語を神話と認定したように、継続的な挑戦の対象であることに留意すべきである。 この用語が大衆社会の概念と結びついたとき、それはより一般的なテーマ、すなわち社会的意味と生活機会や社会的資源の配分の関係、の具体的な変形となるのである。 社会的意味の貯蔵庫とみなされる大衆文化は、ハイカルチャー(あるいはエリート)、アヴァンギャルド文化、フォークカルチャー、ポピュラーカルチャー、そして(後に)ポストモダン文化も含む用語群の一つである。 これらの各カテゴリーの解釈や境界線は、日常的に議論や論争の対象になっている。 このことは、特に表立った定義(各用語の用例の引用や、当該カテゴリーへの配分を正当化するために用いられる理由付け)の試みにおいて明らかになる。 これらの概念の組み合わせにより、差延のシステムが構成され、いずれかの用語の意味の変化は、他の用語との関係の変化を通じて、またそれによって説明可能となるのである。 1366>
Rosenberg and White’s Mass Culture Revisited (1971) の序文で Paul Lazarsfeld は、米国では大衆文化に関する論争と議論が 1935 年から 1955 年の間に最もはっきりと盛んになったことを示唆した。 この時期は、マスメディアが民主主義社会における重要な文化的力であるという認識が、ヒトラーやスターリンの政権やメディア政策に関連した全体主義的な統制の形態の発展と重なった時期であった。 これらの進展の間に見られる親和性は、市民社会の制度、文化一般、そして特にハイカルチャーを、それらが直面する脅威からいかにして守るのが最善であるかの懸念を引き起こした。 このような関心事が、当時の大衆文化に関する議論のパターンを形成するのに役立った。 確かに、アメリカの社会評論家や文化批評家の間では、保守的な思想家と批判的な思想家の違いを超えて、大衆文化に対する反感が広く浸透していたことは確かである。 1366>
批評家の多くにとって、マスカルチャーをハイカルチャーの「他者」として否定的に定義することが典型的な戦略であった(Huyssen 1986)。 このようにマスカルチャーをハイカルチャーにないものすべてとして定義し理解するという収束は、価値づけられたハイカルチャーの概念が(1)一般的に保守的で伝統的、または(2)特にモダニストでアヴァンギャルドであるかもしれない状況のもとで起こったのである。 オルテガ・Y・ガセットやT・S・エリオットの影響を受けた一部の保守派にとって、それはより貴族的で秩序ある過去に対する臆面もないノスタルジアという形をとっている。 したがって、彼らは大衆文化がもたらす脅威を「下」から(「大衆」とその嗜好によって)生み出されたものだと考える傾向があった。 テオドール・アドルノのような批判的理論家にとっては、大衆文化は上(資本の所有者)に由来する利益に奉仕し、それまで産業組織と結びついていた合理性の様式の搾取的拡大の表現であった。 この批評家グループの理解する高モダニズム文化の特質は、自律的、実験的、敵対的、メディアに対する高い反射性、そして個人の天才の産物であること、あるいはむしろそれを目指していることである。 一方、大衆文化は、徹底的に商品化され、型にはまった美的コードを用い、文化的・思想的に適合し、集団的に生産されるが、伝達メディアの経済的要請、組織的ルーチン、技術的要件に従って中央で統制されるというのが、これに対応する視点である。 このような大衆文化の出現は、大衆によって作られるのではなく、大衆のために作られる文化として、大衆文化や民俗芸術と結びついた抵抗と、高等文化が識別される目的の真剣さを閉ざす役割を果たす。 社会科学者との接点となったのは、(社会的プロセスとして理解される)近代の発展が大衆社会の出現と関連しているかどうかという、後者の関連した関心事であった。 このような社会の概念が(組織化された)少数者と(無秩序な)多数者の間の対比に根ざしている限り、社会思想および政治思想におけるその長い前史は古典ギリシャに遡るとGiner(1976)は示唆している。 同様に、テオドール・アドルノは、『オデュッセイア』におけるオデュッセウスのセイレーンとの出会いと、セイレーンの魅惑的な、しかし深く陰湿な魅力に関するホメロスの記述にまでさかのぼり、大衆文化の基盤があると見なしていた
しかしながら、大衆社会に関する社会学特有の理論は、アレクシ・ド・トクビル、ジョン・スチュアート・ミル、カール・マンハイムの著作にその先祖を持ち、まったく最近になってからである。 ウィリアム・コーンハウザーやアーノルド・ローズといった作家によって定式化されたこの理論は、現代社会の全体像を提示するというよりも、むしろ、特定の社会的傾向を強調することに関心をもっていた。 その主張は、典型的には、「伝統的」社会の秩序ある特徴と称されるもの、あるいは、それほど頻繁ではないが、「階級的」社会を例示する連帯、集団性、組織的闘争の形態との様式化された対比によって語られるものである。 簡単に言えば、社会関係は、都市の成長と都市への移動、交通手段とその速度の発展、生産プロセスの機械化、民主主義の拡大、官僚的組織形態の台頭、マスメディアの出現によって変容したと解釈されているのである。 このような変化の結果として、第一次集団のメンバー、親族、コミュニティ、地域性といった原初的な結びつきが薄れてきていることが論じられている。 多元主義の機関として機能し、市民と中央集権的な権力との間の緩衝材として機能しうる効果的な二次団体が存在しない場合、出現するのは不安定で原子化された個人である。 彼らは、当時の影響力のあるイメージで言えば、デイヴィッド・ライズマンとその仲間たちが「孤独な群衆」と呼んだものを構成しているとみなされる。 このような個人の”他者指向”の行動は、伝統によって神聖化されたものでも、内なる信念の産物でもなく、むしろマスメディアや現代社会の流行によって形成されている。
C. Wright Mills (1956) のバージョンでは、関連する(そしてメディア中心の)論文の対比は過去と過去に送ったものよりも、想像の可能性と加速する社会傾向の間にあるものだった。 最も重要な違いは、”mass”の特性と”public”の特性の間にあり、この二つの(理想型)用語は、支配的なコミュニケーション様式によって互いに区別されるものであった。 大衆」とは、(1)事実上、意見を述べる人と受け取る人の数が同じであること、(2)公共のコミュニケーションが組織化されており、表明された意見に迅速かつ効果的に答える機会があること、(3)こうして形成された意見は効果的な行動の出口を見つけること、(4)権威ある機関が大衆に浸透せず、多かれ少なかれ自律的であること、という古典的民主主義の理論の規範的基準と整合的なものである。 1366>
これらのイメージが暗示するように、またその後スチュアート・ホールが示唆したように、大衆文化についての議論の背後にあったのは、(それほど)隠されていなかった”大衆”の主題であった。 しかし、これはレイモンド・ウィリアムズがその存在自体に疑念を表明したことで有名な社会的カテゴリーであり、常に自分たち以外の人間から構成されているように見えると辛辣な指摘をしていたのである。 このような懐疑論は、ウィリアムズとは全く異なる思想家であるダニエル・ベル(1962)にも共有されていた。 大衆社会としてのアメリカという概念を批判する中で、彼は「大衆」という言葉の周りに集まっているしばしば矛盾した意味や連想を指摘した。 それは、異質で差別化されていない聴衆、無能な者による判断、機械化社会、官僚化社会、暴徒、あるいはこれらの組み合わせといった意味にされるかもしれないのである。 1366>
さらに、1960 年代には、大衆文化概念の形式的、認識的基盤の空洞化が、より直接的な経験的課題によって補完されつつあった。 若者を中心としたカウンターカルチャーの出現、公民権運動、ベトナム戦争への反対、第二波フェミニズムの出現、そして、これらの発展を記録すると同時に助長するメディアの役割の矛盾と両義性はすべて、大衆社会というテーゼに疑問を投げかける役割を果たしました。 さらに、一握りの大手企業によるポピュラー音楽産業の支配(ピーターソン & バーガー 1975)と大手スタジオによる映画制作は、独自の優先事項を持つ独立した文化プロデューサーからの深刻な挑戦を受けていた(Biskind 1998)。 その結果、(少なくとも、最終的に企業の支配が再び強まるまでの10年間は)メディア文化がまったく多様化することになった。 また、以前の正統派に対する反発や挑発として説明できるかもしれないが、大衆文化という概念そのものを支持するポピュリスト風の学術的な事例も出現した–たとえば、『大衆文化』誌のように。 この後者の傾向が、時にエフェメラに対する無反省な熱意や制度分析の軽視を示すことがあったとしても、それは、1970年代に明らかになった大衆文化の多様性に対するより広範な認識(例えば、Gans 1974)を先取りしていた。
1980年代、ポストモダンという概念が持続的に批判されるようになると、大衆文化形式の文化受容を重視した実証研究が革新的に行われ(Radway 1984; Morley 1986)、注目されるようになった。 ポストモダニズムは、マス・カルチャーに対するハイ・モダニズムの反感を一切示していない。 それどころか、文化的境界の曖昧さを示す証拠が増えるにつれ、ポストモダンイズムの実践者たちは、「ハイ」と「マス」の対比やそれを支える階層的区別の根拠そのものに疑問を投げかけるか(Huyssen 1986)、(やや平然と)それを無視するようになったのである。 たとえば、テレビのソープオペラに関する研究は、複数のプロットライン、物語の終結の不在、テキストの境界の問題化、このジャンルとその視聴者の文化的状況との関わりといった構造的複雑性に注意を向けることで、このようなテキストに対する批判的軽蔑という慣習を覆した(Geraghty 1991)
その「クラシック」な形で、マスカルチャー/マスソサエティ論文は説得力の多くを失ってしまったのである。 それでも、その主張の現代的な変容は、たとえば、ギー・ドゥボールやジャン・ボードリヤールのポスト・マルクス主義の著作や、博識な保守派評論家ジョージ・スタイナーによる、文化の質と民主主義の両方が可能であると主張するのは不誠実であるという主張などに見て取ることができる。 シュタイナーは選択の必要性を主張している。 しかし、この論文で最も永続的かつ有望な遺産となりうるのは、密接に関連する「文化産業」という概念への改良である(Hesmondhalgh 2002)。 文化産業は、アドルノとその同僚マックス・ホルクハイマーによって、「大衆文化」よりも受け入れられやすい用語として認識されていた。 この用語は、元来、文化支配の概念としては、あまりにも陰鬱で全体化しすぎたものであった。 メディア・テキストの多義性やメディア視聴者の機知に重点を置くことは、重要な方法論的是正をもたらすものであった。 しかし、これらのアプローチもまた過剰になり、過去10年間におけるメディア生産のグローバル化やメディア研究者の間での制度分析および政治経済の復活により、文化産業概念への関心が復活した。 批評. において。 イデオロギーの終焉. 5400>
Back to Top
Back to Sociology of Culture.
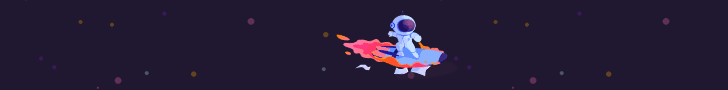
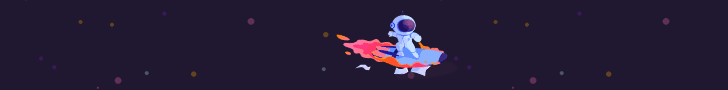
3054




